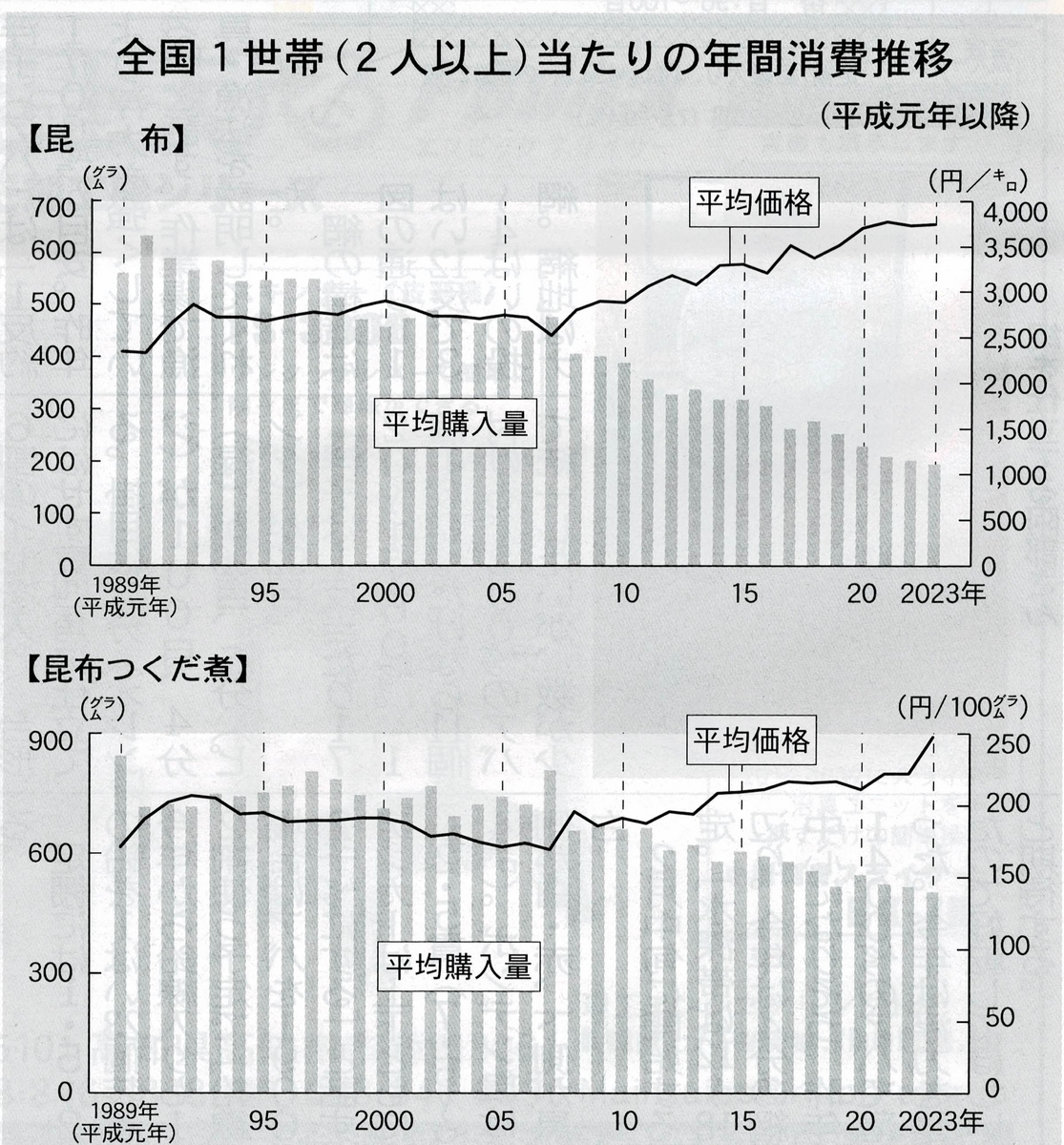さて、世に伝わる情報の真偽。
それを見極めるのは、本当に難しいものです。
特に大手企業による発信は、一般的に信用度が高いと見なされがちで、尚且つ拡散力も強いだけに、誤情報が伝わった場合の弊害も大きいでしょう。
例えば、「うまみ」が減塩に効果的だとの説は、うまみ調味料メーカーが主導して流布され、もはや一般的になったように思います。
下記ウェブサイトのような内容です。
しかし、私はこれに反対する投稿を2023年の2月に書いているのです。
今日の投稿は新たな視点も加えまして、より深い内容になっています。
全ての食品カテゴリーについて「正しくない」と断言できるかどうかは分かりませんが、読んでいただければ納得していただけるかと思います。
段落としては、
①うまみ調味料業界が言うところには
②うまみ調味料の有無と塩分量の相関の例
③しょっぱくない塩
④塩とうまみ調味料は、相性が良い
⑤弊害「たん白質量の誤認」
⑥成立しない仮定に基づく主張
と順に書きたいと思います。
それでは、まず
①うまみ調味料業界が言うところには
まず、うまみ調味料業界は「うまみ調味料で減塩できる」と主張するわけですが、その仕組みを下記のウェブサイト内で説明されています。
抜粋しますと、
『うま味成分であるグルタミン酸ナトリウム(MSG)のナトリウム含有量は、食塩の3分の1以下です。家庭での調理時、食塩を減らしてMSGを加えることで、例えば汁物ではおいしさはそのままに、約30%のナトリウムを減らすことができます。』
この表現方法は、非常に巧妙に仕組まれた罠でありまして。
それは、「食塩を減らし、それをうまみ調味料で代替する」との仮定の元に書かれている点です。
しかし多くの場合、そんな仮定は成立しないと私は考えています。
理由は簡単で、それでは美味しくないからです。
それを、具体的な事例を元に次の段でご説明します。
②うまみ調味料の有無と塩分量の相関の例
2023年2月の過去投稿では三つの食品を例に挙げ、「うまみ調味料で減塩」が疑わしいと感じる理由について書きました。
「レトルトカレー」「ポテトチップス」「たまご豆腐」の三食品で、うまみ調味料入りの製品の方が、塩分量が高い傾向にあることをご説明しました。
しかし、我が事ながら非常に抜けた話ですが、自社製品の例を挙げる方がよほど適切だったようです。
それは、「塩ふき昆布」です。
昆布の同業者のことですからあまり悪く言いたくはないのですが、本日は下記の大手メーカー2社の製品と、こんぶ土居製品を比較します。
まず、比較品の原材料は以下の通りです。
〇『ふじっ子 塩こんぶ』
「昆布、しょうゆ、たんぱく加水分解物、砂糖、昆布エキス、食塩/調味料(アミノ酸等)」
〇『くらこん 塩こんぶ』
「昆布 (北海道産)、醤油 (大豆・小麦を含む)、食塩、醤油加工品 (大豆・小麦を含む)/調味料 (アミノ酸等)、甘味料 (ソルビトール、甘草)、増粘多糖類」
調味料(アミノ酸等)、が読み取れるので、共にうまみ調味料を含んでいます。
また栄養成分表示から読み取れる製品100g中の「食塩相当量」は、それぞれ以下の通り。
◆フジッコ 塩こんぶ
食塩相当量22.5g
◆くらこん 塩こんぶ
食塩相当量23.9g
これに対しまして。
こんぶ土居の「細切しおふき」。
原材料は下記の通りです。
真昆布(北海道函館市産)
丸大豆醤油(和歌山県東牟婁郡製造)(原材料:丸大豆、小麦、塩)
濃縮だし(大阪府製造)(原材料:真昆布、鰹節、鰯煮干し)
たまり醤油(三重県鈴鹿市製造)(原材料:丸大豆、塩)
伝統味醂(岐阜県加茂郡製造)(原材料:もち米、米麹、米焼酎(乙類))
純米酒(長野県佐久市製造)(原材料:米、米麹)
和三盆糖(徳島県製造)(原材料:さとうきび、砂糖)
ご覧いただける通り、うまみ調味料は一切含んでいません。
そしてこの製品100gに含有する「食塩相当量」は、たったの「8.9g」です。(株式会社食品微生物センター調べ)
先にご紹介した他社2製品は「22.5g」と「23.9g」でしたから、半分以下です。
ちなみに、前述の他社製品には減塩バージョンも存在するようで、そちらも比較に用います。
原材料は以下の通りで、たんぱく加水分解物や酵母エキス等のうまみ調味料は含まれていますが、所謂化学調味料と呼ばれる「アミノ酸等」は含まれていないのが見て取れます。
原材料名 :昆布(北海道産)、醤油(大豆・小麦を含む)、砂糖、水あめ、たんぱく加水分解物(大豆を含む)、乳糖、醸造酢、食塩、酵母エキス、寒天、かつおエキス、でんぷん
また栄養成分については、食塩相当量 2.8g(1袋27gあたり)と公開されていますので
他の製品と同様に製品100gあたりで換算しますと、食塩相当量10.4gという数字になります。
整理しますと。
食塩相当量22.5g
◆くらこん 塩こんぶ(「調味料 (アミノ酸等)」入り)
食塩相当量23.9g
◆くらこん 減塩塩こんぶ(「調味料 (アミノ酸等)」なし) 《酵母エキスは入っています》
食塩相当量10.4g
◆こんぶ土居 細切しおふき(すべてのうまみ調味料なし)
食塩相当量8.9g
これを見れば、「うまみ調味料の使用」と「含有する食塩相当量」には、正の相関関係がありそうなのは、誰の目にも明らかでしょう。
うまみ調味料業界が主張する「うまみ調味料で減塩」の真逆です。
なぜこんな結果になるか。
その理由について、次の段落でご説明したいと思います。
③しょっぱくない塩
「塩味」という味覚は、裏腹の要素を含んでいます。
塩分は人体に欠くことのできない栄養素ですし、つまり『塩は間違いなく美味しい』でしょう。
しかしその一方、舌を刺すような刺激も含みます。
その刺激があるからこそ、多いと「しょっぱすぎる」という嫌な感覚につながるわけです。
適切な濃度が大切です。
では仮に、「しょっぱすぎない塩」が存在したとしたら、どうなりますでしょうか。
「しょっぱすぎる」という嫌な感覚に繋がりにくいわけですから、必然的に使いすぎが起きやすいでしょう。
実際に「しょっぱすぎない塩」をつくることは簡単で、うまみ調味料を混ぜれば良いのです。
製品で言えば「アジシオ(味の素株式会社が製造する、食塩とグルタミン酸ナトリウムの混合品)」などは、正にそれに当たります。
普通の塩とアジシオ、両者の味比較をしていただければ、私が申し上げていることを感覚から理解していただけるかと思います。
そもそも、「塩カドを感じること」や「しょっぱ過ぎると感じること」は、塩分を取り過ぎないようにするために、人体に備わっている防御作用なのだと思います。
アジシオの例の通り、うまみ調味料がその防御反応を麻痺させ、「しょっぱすぎない塩分」「塩味を感じにくい塩分」が実現するわけですから、過剰に使うことになるのは当たり前でしょう。
それを、「塩ふき昆布」の事例は示しているのではないでしょうか。
私共の製品は、減塩を追求したものではありません。
たいしてレシピも変えず数十年、私共が考える「おいしさ」を追求してつくってきました。
例えば、この製品の製造時に醤油を増量したり、比較品のように食塩を併用すれば、当然に含有塩分量は増します。
しかし、そんなことをすれば「しょっぱすぎる」製品になります。
その一方、大手2メーカーの製品は私共の製品の2倍以上の塩分量が含まれているわけですが、それでいて尚「しょっぱすぎない」のです。
こんなパラドックスを成立させてしまうのが、うまみ調味料です。
④塩とうまみ調味料は、相性が良い
食べ物には、相性があります。
それは、うまみ調味料でも同じで、合うものと合わないものがあるのです。
今や、スーパー等で売られている加工食品には、ほとんどの場合「調味料(アミノ酸等)」と表記される、うまみ調味料が含まれています。
「化学調味料不使用」を謳う製品であっても、類似の効果の「たん白加水分解物」や「酵母エキス」等が入っているものです。
しかし一方、甘い物にうまみ調味料が入ることは、ほとんど無いと言って良いでしょう。
和洋問わず、砂糖が使われる菓子の類の原材料表示欄に「調味料(アミノ酸等)」の表記を見ることは、ほとんどありません。
つまり、うまみ調味料は、「塩分を含む食品と相性がよく、甘い食品と相性が悪い」のだと思います。
多くの方に、体験として納得していただけるでしょう。
これについては、うまみ調味料の産みの親である池田菊苗氏も言及しているところであって、1912年の報告書にて「食塩と組み合わせると特に味が良くなる」と書いています。
(「グルタミン酸塩の味について」 (1912年 東京帝国大学理学部 池田菊苗) より)
「食塩とうまみ調味料が、味覚的相性が良い」。
この事実を見れば、「うまみ調味料を使うことによって減塩につながる」なんてはずがなく、お互いに引き合って、共に使うことに繋がりやすいのは、当然だと思われませんでしょうか。
⑤弊害「たん白質量の誤認」
さて前述のように、ご紹介した他社のしおふき昆布にはうまみ調味料が含まれているわけですが、その量は、どうやら非常に多いようです。
それは前述の『②うまみ調味料の有無と塩分量の相関関係』と同様、栄養成分の分析によって見えてきます。
公開されているデータから、食塩相当量と共にたんぱく質量を併記します。(製品100g中)
製品① フジッコ 塩こんぶ(「調味料 (アミノ酸等)」入り)
たんぱく質 24.6g、食塩相当量22.5g
製品② くらこん 塩こんぶ(「調味料 (アミノ酸等)」入り)
たんぱく質 27.1g、食塩相当量23.9g
製品③ くらこん 減塩塩こんぶ(「調味料 (アミノ酸等)」なし) 《酵母エキスは入っています》
たんぱく質 8.5g、食塩相当量10.4g
製品④ こんぶ土居 細切しおふき(すべてのうまみ調味料なし)
たんぱく質 11.9g、食塩相当量8.9g
所謂化学調味料「調味料(アミノ酸等)」を含む①と②が、圧倒的にたん白質量が多いです。
この差こそが要注意なのですが、何故たん白質量とうまみ調味料が関係するのでしょうか。
以下の文部科学省のサイトに詳しいですが、食品に含有する「たん白質量」を計算する際の手法としては、「アミノ酸量」又は「窒素量」が使われています。
そして、表示上で調味料(アミノ酸等)と書かれるうまみ調味料は、主成分が「グルタミン酸ナトリウム」であり、グルタミン酸はアミノ酸の一種です。
つまり、「調味料(アミノ酸等)」を多量に使うということは、それ即ち「アミノ酸含有量が多い」ということに繋がり、同時に栄養成分表示上での「たん白質量の数値が増える」ことも意味するのです。
そもそも、しおふき昆布は、昆布を醤油や味醂などの調味料で煮て乾燥させた製品ですから、本来は特にたん白質が豊富ではありません。
それでいて、「調味料(アミノ酸等)」無しの
製品③ くらこん 減塩塩こんぶ、「たん白質含有量、8.5g」
製品④ こんぶ土居 細切しおふき、「たん白質含有量11.9g」
に比べて、「調味料(アミノ酸等)」ありの
製品① フジッコ 塩こんぶ、「たん白質含有量、24.6g」
製品② くらこん 塩こんぶ、「たん白質含有量、27.1g」
が圧倒的にたん白質含有量の多いこと。
それは、「調味料(アミノ酸等)」に由来すると考えるのが妥当で、含有量の差の分だけ化学調味料が使われているのだとすれば、こういった製品には本当に多量のうまみ調味料が含まれているのだと思います。
表示上、見かけのたん白質含有量が多くなっているのは、こんな仕組みだと考えています。
これは現在の栄養成分表示の欠陥のひとつであって、「非必須アミノ酸」である食品添加物のグルタミン酸ナトリウムであれ、アミノ酸スコアの高い自然のたん白質であれ、とにかくアミノ酸が多ければ即ち「たん白質豊富」と見えてしまうわけです。
肉や魚、大豆など、自然のたん白質豊富な食品でなくても、うまみ調味料を多量に含めば、表面的に「タンパク質豊富な食品に映る」、これは大変に大きな問題だと思います。
アミノ酸スコアの大切さについては、過去投稿でも書いていますので、是非ご参照下さい。
更に、たん白質量から含まれるうまみ調味料の多寡を推定する試みは、本日のメインテーマである「減塩になどつながらない」という私の主張の補強にもつながるのです。
2023年2月の投稿で例として取り上げた「レトルトカレー」「ポテトチップス」「たまご豆腐」の三食品では、「どちらかと言えば、うまみ調味料入りの製品が塩分量も多い傾向にある」といった程度の差でした。
しかし今回のしおふき昆布の例は、そんなレベルで無いのはご紹介した通り。
たんぱく質量に影響を及ぼすほど多量に使えば使うほど、それに伴って塩分含有量も大きく増えてくるわけです。
どの角度から見ても、うまみ調味料業界の主張と真逆の現実が見えてきます。
⑥成立しない仮定に基づく主張
冒頭に書いた通り、うまみ調味料メーカーが主張する減塩効果とは、「食塩を減らし、それをうまみ調味料で代替する」ということを条件にしています。
そんなことが実際に成立する食品も、中にはあるのかも知れません。
しかし、今回の事例で見える通り、多くの場合代替などされません。
むしろ逆で、
『うまみ調味料を入れたら、その分塩分も多めに入れないと味のバランスが取れない。』
が正解でしょう。
ある仮定の元に話を進めておきながら、その仮定が現実に広く成立しているかどうかの検証が全く不十分です。
どんな実験データに基づいて主張されているのかは分かりませんが、市販製品という何よりの「現実」「実例」と食い違うわけで、不適切だと言わざるを得ません。
是非是非、お気をつけください。
『まとめ』
繰り返しになりますが、下記の過去投稿でも、うまみ調味料の問題点は指摘しました。
私もうまみ調味料の存在を全否定するつもりはありません。
しかし、「文化を破壊し」「健康を害する」、この2点だけは間違いないかと思います。
「うまみ調味料が減塩に効果的」などという誤った健康イメージを植え付けることは、是非やめるべきだと思うのですが。
さてさて皆様方、いかがお考えでしょうか。
(了)
#うまみ調味料
#うまみ
#減塩
#ウソ
#嘘